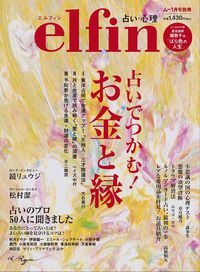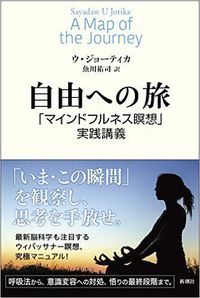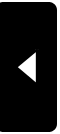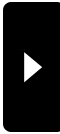「ミャンマーの瞑想」。
マハーシ長老が著した世界的名著です。


日本語訳は、1996年に、
ウ・ウィジャナンダー大僧正が翻訳して、
「国際語学社」より出版されています。
この書は、本当に名著です。
マハーシ式の「ラベリング」の指南書です。
「清浄道論」の「七清浄」にしたがい、
ヴィパッサナ瞑想による「十六観智」が
生じ深まっていく進展をマニュアル化しています。
1.戒清浄
2.心清浄
3.見清浄・・・名色分離智
4.度疑清浄・・・縁摂受智
5.道非道智見清浄・・・思惟智、生滅智
6.行道智見清浄・・・壊滅智、怖畏智、過患智、厭離智、脱欲智、省察智、行捨智、随順智、種姓智
7.智見清浄・・・道智、果智、観察智
ところが「ミャンマーの瞑想」は、
何度か絶版になっています。
版権も変わっているみたいですね。
2011年には「アルマット」から出版されています。


2016年からは「サンガ」から出版されています。
今は「サンガ」に版権があるんでしょうか。


◆瞑想中に生じる奇景八触にも言及している優れた書
「ミャンマーの瞑想」は優れたマニュアルです。
たとえばヴィパッサナ瞑想中に起きる
心身の異変についても言及があります。
身体がゆれる、めまいがする、虫がはっている、
体がふくらんだ感じになる、体が消えたようになる、
不思議なビジョンを見るなどの
奇妙な感覚になることについてですね。
こうした心身の奇妙な感覚は、
気功におけるいわゆる「奇景八触」です。
奇景八触は「動、痒、重、軽、涼、暖、滑、粗」という
八種類の感覚をいいます。
こうした奇妙で特有な感覚は気功や瞑想をしていると
出てくることがあります。
気(プラーナ、アパーナなど)が関係しています。
神智学でいうところのエーテル体で起きている現象ですね。
◎95. 気の感覚ーー「八触」: 朱剛気功話
◎17.「奇景八触」について: 朱剛気功話
こうした感覚が起き得ることを知りませんと、
「病気になった」とか、「おかしくなった」と
変に思い込んでしまうこともあるでしょう。
また中には「体が消えた」ことを「空を体験した」とか「悟った」として
早合点してしまうこともあるでしょう。
けれどもこれらは「神秘体験」や「妄想」です。
また中には自我が肥大して高飛車で傲慢、
鼻持ちならない性格になってしまうこともありますので、
こうした心身の変容には注意してまいる必要があります。
「奇景八触」は「魔境」という言い方もできますが、
魔境は奇景八触がリアルと信じ込んだり、
定着してしまったときのメンタリティ等をいっていると思いますね。
スルーしていれば問題はないでしょう。
気功と同じで、意識が深い状態になると
潜在的に有している様々なものが表出し、
それが「奇景八触」といわれる
不思議な状態を引き起こします。
やたらと「魔境」とかいって
あまり大騒ぎをしないほうがいいと思います。
瞑想をしていると「奇景八触」に遭遇することもありますが、
そのときに心の状態は身体の状態をホンモノと思い込むと
いわゆる「魔境」になってしまうと思います。
心が増幅し、自分が大きくなった感じになり、
それを剛胆で気宇広大になったか思い込んで、
自我の肥大を引き起こすことは、
昔から瞑想や禅の世界で起きています。
「奇景八触」にとらわれるからおかしくなるわけでして、
とらわれなければ一過性の現象としてみなすことができます。
「ミャンマーの瞑想」には、
こうした「奇景八触」が起きることについて
ちゃんと述べられています。
「奇景八触」という言葉は使っていませんが、
心身に異変が起きることをきちんと指摘しています。
こうした指南書は他にありません。
大変優れていると思う理由の一つですね。
まさに実践を通して書かれていることが
わかるわけなんですね。
単に清浄道論に沿って書いているのとは違います。
「ミャンマーの瞑想」も、
テーラワーダ本ではおすすめの書です。
希有の書といっていいでしょう。
大変参考になります。
◆道果についても言及のある「ミャンマーの瞑想」
さらに「ミャンマーの瞑想」は、「道果(どうか)」
についても詳しく述べています。
ちなみに「道果」とは、涅槃を体験したことをいいますね。
テーラワーダでは「果(か)」といっています。
「ミャンマーの瞑想」には、道果にいたった状態を
次のように述べています。
・念じられた対象と念じる心、
すべてが共にきっちり切れて停止してしまった
・ぶら下がっている巨大な蔓つるを刀で切り落としたように、
対象と念じる心はストンと切断されてしまった
・担いできた重荷を投げ出したように、
対象と念じる心、すべてが抜け落ちてしまった
・手に握り、ぶら下げた物が急に取れて落ちるように、
対象と念じる心すべてが取れて落ちてしまった
・危機または監禁から突然逃れたように、
対象と念じる心から解放された
・対象と念じる心が停止し滅尽したのは、
小さな炎が突然消えてしまうように、非常に速やかだ
・暗闇から明け方に急に出て来たように、
対象と念じる心から逃れ出た
・ゴタゴタした所からスッキリした所に突然到着したように、
対象と念じる心から脱出した
・石が水にたちまち沈んでしまうように、
対象と念じる心は沈没してしまった
・疾走している人が真正面から蹴とばされたように、
対象と念じる心は急止してしまった
・対象と念じる心は滅亡してしまった
また、この記述の直後に、
諸行の停止している状態を体験した期間は、
さほど長く続いたわけではありません。
ごくわずか、一刹那程度の念じる瞬間のようなつかの間です。
後になってこうした様子を、聖者は顧みて観察するのです。
とあります。
これは禅でいうところの「見性(けんしょう)」ですね。
見性。
見性も「一刹那程度の瞬間」に起きます。
同じです。
最初は「有身見(うしんけん)」が切れるといわれています。
「自己と身体とを同一視」している見解ですね。
マハーシ長老のテキストでは、最初の道果(見性)では、
「対象と念じる心が切断された」といった
パターン化された表現が取られていますが、
これは「涅槃(空)」をリアルに体験体感したことを
表現したものではないかと推察いたします。
◆道果の際には身体の崩壊感をともなうことが多い?
ちなみにパーリ仏典の古い層では、道果を体験した際に
「身体の崩壊」感で表現されることが多いといわれています。
このことは中村元先生が「原始仏教の思想」の中でも述べています。


パーリ仏典では「身体の壊滅」の感覚が
「涅槃」と関係がある表現をとって伝承もされているといいます。
一例をあげますと、
自己の身体を断滅することが「安楽」である。
[スッタニパータ761]
蛇が身の抜け殻を捨て去るように、この身を捨て去る。
[テーラーガータ576]
身体を壊(やぶ)り、表象作用と感受作用とを静めて、
識別作用を滅ぼすことができたならば、苦しみが終滅すると説かれる。
[ウダーナヴァルガ第26章ニルヴァーナ16]
こうした表現ですね。
「身体の断滅」「蛇が身の抜け殻を捨て去るように」「身体を壊(やぶ)る」
といった具合で、「この身体が自分という感覚(自己同一性)」が
崩れ去ったとき、違っていたんだという自覚が生じたときに
最初の涅槃を体験するといったことなのでしょう。
もっともこれは「有身見」の断滅にとどまった感覚ではなく、
涅槃そのものに完全にいたった状態を
表現しているのかもしれませんね。
【参考記事】
◎有身見と身体の崩壊~アーチャン・チャー
https://healingmusic.hamazo.tv/e5511579.html
◆アーチャン・チャーと玉城康四郎氏も「身体の壊滅」を体験
ちなみにアーチャン・チャーも、悟った瞬間に
「身体の壊滅」感が起きたことを述べています。
アーチャン・チャーの「手放す生き方」p251には、
悟ったときの体験として、次の記述があります。
「大音響とともに私の身体は木っぱ微塵に砕け散りました」。
「木っぱ微塵に砕け散る」。
まさに「身体の壊滅」感です。

また東京大学の教授だった玉城康四郎氏も
著書「ダンマの顕現」の中で、自らの「見性」体験を述べていますが、
やはり同じように「身体の壊滅」感があったことを述べています。
奇しくもアーチャン・チャーと同じ「木っ端微塵」と言っています。
要約して引用しますと、
「十地経を取り出して見ていたところ、
何の前触れもなく突然、大爆発した。
木っ端微塵、雲散霧消してしまったのである。」
とあります。
アーチャン・チャーと同じように「木っ端微塵」と表現しています。
「身体の壊滅」感です。
「爆発」。
玉城康四郎氏の「身体の爆発」「木っ端微塵」の感覚は、
「有身見」が断滅する体験であろうと思います。


◆「見性」「有身見が切れる」ときに身体の崩壊感をともなう
で、この悟った瞬間に感じる「身体の壊滅」感は、
「見性(けんしょう)」したときの感覚として、
表現されることがあります。
「見性」を最初にするときは、理屈の上からいっても、
「有身見」が切れることになりますね。
「有身見」とは「この肉体が自分であると思い込んでいる自己同一性」の見解ですね。
これが切れてしまうのでしょう。
このときに「爆発」「木っ端微塵」、あるいは「自他との区別がなくなる」
「自分が消え去って、大いなる存在に取って代わる」といった、
時空を超越した衝撃的な「身体の壊滅」感をともなうのでしょう。
中でも最初の「有身見」が切れるとき、
いわゆる最初の「見性(道果)」では、
身体が爆発してしまう「壊滅感の体験」を
するのではないかと思います。
「見性(道果)」の際に「有身見」が切れるときは、
今まで「この肉体、身体」が「自分」と思い信じ込んできたものの、
その瞬間に「この肉体、身体は自分でない」ということを
空や爆発感、衝撃、一瞬の拡大感などとともに
豁然として如実に体感します。
これは時空を超えた超越的感覚をともない、
想像や妄想、あるいはアストラル界的な瞑想体験とは
まったく異なる感覚をもたらします。
一刹那の瞬間に体験しますが、
それはもう「悟り」としか言いようのない
強烈かつ本能的な印象とともに、
その人に恒久的な魂の刷新性と、
まったく新しい何かに開けた感覚を与える、
そんな体験が「見性」とか「悟り体験」といった
覚醒体験なのではないかと思います。
おそらくこれが「有身見」が切れる瞬間であり、
「見性(道果)」の体験ではないかと推察いたします。
マハーシ長老の「ミャンマーの瞑想」では、
「対象と念じる心は切断された」といった
一つの公式化したパターン表現となっている感も受けます。
時空を超越した体感を表現したものかもしれませんね。
◆ウ・ウィジャナンダー大僧正と世界平和パゴダ
そういわけでして「ミャンマーの瞑想」は大変、
示唆にも富んでいる書だったりします。
ヴィパサナ瞑想中に起きる身体の異変、
また「道果」に至ったときの体験、
大変興味深くまた参考になります。
ちなみに翻訳されたウ・ウィジャナンダー大僧正は、
北九州市にある「世界平和パゴダ」に在住されていましたね。
◎世界平和パゴダ
http://www.worldpeace-pagoda.net/index.html
◎ふるさと探訪|世界平和パゴダ
http://www.nhk.or.jp/kitakyushu/furusato_tanbo/kitakyushu_09.html
◎ミャンマー仏教を語る:世界平和パゴダの可能性
http://amazon.co.jp/dp/4774514683
ウ・ウィジャナンダー大僧正が翻訳してくださったお陰で、
マハーシ長老の名著「ミャンマーの瞑想」を
拝読することもできますね。
ありがたい限りです。
![ミャンマーの瞑想[マハーシ長老]~道果の状態と奇景八触にも言及した希有の名著 ミャンマーの瞑想[マハーシ長老]~道果の状態と奇景八触にも言及した希有の名著](//img01.hamazo.tv/usr/h/e/a/healingmusic/myanmameisou.jpg)
マハーシ長老が著した世界的名著です。

日本語訳は、1996年に、
ウ・ウィジャナンダー大僧正が翻訳して、
「国際語学社」より出版されています。
この書は、本当に名著です。
マハーシ式の「ラベリング」の指南書です。
「清浄道論」の「七清浄」にしたがい、
ヴィパッサナ瞑想による「十六観智」が
生じ深まっていく進展をマニュアル化しています。
1.戒清浄
2.心清浄
3.見清浄・・・名色分離智
4.度疑清浄・・・縁摂受智
5.道非道智見清浄・・・思惟智、生滅智
6.行道智見清浄・・・壊滅智、怖畏智、過患智、厭離智、脱欲智、省察智、行捨智、随順智、種姓智
7.智見清浄・・・道智、果智、観察智
ところが「ミャンマーの瞑想」は、
何度か絶版になっています。
版権も変わっているみたいですね。
2011年には「アルマット」から出版されています。

2016年からは「サンガ」から出版されています。
今は「サンガ」に版権があるんでしょうか。

◆瞑想中に生じる奇景八触にも言及している優れた書
「ミャンマーの瞑想」は優れたマニュアルです。
たとえばヴィパッサナ瞑想中に起きる
心身の異変についても言及があります。
身体がゆれる、めまいがする、虫がはっている、
体がふくらんだ感じになる、体が消えたようになる、
不思議なビジョンを見るなどの
奇妙な感覚になることについてですね。
こうした心身の奇妙な感覚は、
気功におけるいわゆる「奇景八触」です。
奇景八触は「動、痒、重、軽、涼、暖、滑、粗」という
八種類の感覚をいいます。
こうした奇妙で特有な感覚は気功や瞑想をしていると
出てくることがあります。
気(プラーナ、アパーナなど)が関係しています。
神智学でいうところのエーテル体で起きている現象ですね。
◎95. 気の感覚ーー「八触」: 朱剛気功話
◎17.「奇景八触」について: 朱剛気功話
こうした感覚が起き得ることを知りませんと、
「病気になった」とか、「おかしくなった」と
変に思い込んでしまうこともあるでしょう。
また中には「体が消えた」ことを「空を体験した」とか「悟った」として
早合点してしまうこともあるでしょう。
けれどもこれらは「神秘体験」や「妄想」です。
また中には自我が肥大して高飛車で傲慢、
鼻持ちならない性格になってしまうこともありますので、
こうした心身の変容には注意してまいる必要があります。
「奇景八触」は「魔境」という言い方もできますが、
魔境は奇景八触がリアルと信じ込んだり、
定着してしまったときのメンタリティ等をいっていると思いますね。
スルーしていれば問題はないでしょう。
気功と同じで、意識が深い状態になると
潜在的に有している様々なものが表出し、
それが「奇景八触」といわれる
不思議な状態を引き起こします。
やたらと「魔境」とかいって
あまり大騒ぎをしないほうがいいと思います。
瞑想をしていると「奇景八触」に遭遇することもありますが、
そのときに心の状態は身体の状態をホンモノと思い込むと
いわゆる「魔境」になってしまうと思います。
心が増幅し、自分が大きくなった感じになり、
それを剛胆で気宇広大になったか思い込んで、
自我の肥大を引き起こすことは、
昔から瞑想や禅の世界で起きています。
「奇景八触」にとらわれるからおかしくなるわけでして、
とらわれなければ一過性の現象としてみなすことができます。
「ミャンマーの瞑想」には、
こうした「奇景八触」が起きることについて
ちゃんと述べられています。
「奇景八触」という言葉は使っていませんが、
心身に異変が起きることをきちんと指摘しています。
こうした指南書は他にありません。
大変優れていると思う理由の一つですね。
まさに実践を通して書かれていることが
わかるわけなんですね。
単に清浄道論に沿って書いているのとは違います。
「ミャンマーの瞑想」も、
テーラワーダ本ではおすすめの書です。
希有の書といっていいでしょう。
大変参考になります。
◆道果についても言及のある「ミャンマーの瞑想」
さらに「ミャンマーの瞑想」は、「道果(どうか)」
についても詳しく述べています。
ちなみに「道果」とは、涅槃を体験したことをいいますね。
テーラワーダでは「果(か)」といっています。
「ミャンマーの瞑想」には、道果にいたった状態を
次のように述べています。
・念じられた対象と念じる心、
すべてが共にきっちり切れて停止してしまった
・ぶら下がっている巨大な蔓つるを刀で切り落としたように、
対象と念じる心はストンと切断されてしまった
・担いできた重荷を投げ出したように、
対象と念じる心、すべてが抜け落ちてしまった
・手に握り、ぶら下げた物が急に取れて落ちるように、
対象と念じる心すべてが取れて落ちてしまった
・危機または監禁から突然逃れたように、
対象と念じる心から解放された
・対象と念じる心が停止し滅尽したのは、
小さな炎が突然消えてしまうように、非常に速やかだ
・暗闇から明け方に急に出て来たように、
対象と念じる心から逃れ出た
・ゴタゴタした所からスッキリした所に突然到着したように、
対象と念じる心から脱出した
・石が水にたちまち沈んでしまうように、
対象と念じる心は沈没してしまった
・疾走している人が真正面から蹴とばされたように、
対象と念じる心は急止してしまった
・対象と念じる心は滅亡してしまった
また、この記述の直後に、
諸行の停止している状態を体験した期間は、
さほど長く続いたわけではありません。
ごくわずか、一刹那程度の念じる瞬間のようなつかの間です。
後になってこうした様子を、聖者は顧みて観察するのです。
とあります。
これは禅でいうところの「見性(けんしょう)」ですね。
見性。
見性も「一刹那程度の瞬間」に起きます。
同じです。
最初は「有身見(うしんけん)」が切れるといわれています。
「自己と身体とを同一視」している見解ですね。
マハーシ長老のテキストでは、最初の道果(見性)では、
「対象と念じる心が切断された」といった
パターン化された表現が取られていますが、
これは「涅槃(空)」をリアルに体験体感したことを
表現したものではないかと推察いたします。
◆道果の際には身体の崩壊感をともなうことが多い?
ちなみにパーリ仏典の古い層では、道果を体験した際に
「身体の崩壊」感で表現されることが多いといわれています。
このことは中村元先生が「原始仏教の思想」の中でも述べています。

パーリ仏典では「身体の壊滅」の感覚が
「涅槃」と関係がある表現をとって伝承もされているといいます。
一例をあげますと、
自己の身体を断滅することが「安楽」である。
[スッタニパータ761]
蛇が身の抜け殻を捨て去るように、この身を捨て去る。
[テーラーガータ576]
身体を壊(やぶ)り、表象作用と感受作用とを静めて、
識別作用を滅ぼすことができたならば、苦しみが終滅すると説かれる。
[ウダーナヴァルガ第26章ニルヴァーナ16]
こうした表現ですね。
「身体の断滅」「蛇が身の抜け殻を捨て去るように」「身体を壊(やぶ)る」
といった具合で、「この身体が自分という感覚(自己同一性)」が
崩れ去ったとき、違っていたんだという自覚が生じたときに
最初の涅槃を体験するといったことなのでしょう。
もっともこれは「有身見」の断滅にとどまった感覚ではなく、
涅槃そのものに完全にいたった状態を
表現しているのかもしれませんね。
【参考記事】
◎有身見と身体の崩壊~アーチャン・チャー
https://healingmusic.hamazo.tv/e5511579.html
◆アーチャン・チャーと玉城康四郎氏も「身体の壊滅」を体験
ちなみにアーチャン・チャーも、悟った瞬間に
「身体の壊滅」感が起きたことを述べています。
アーチャン・チャーの「手放す生き方」p251には、
悟ったときの体験として、次の記述があります。
「大音響とともに私の身体は木っぱ微塵に砕け散りました」。
「木っぱ微塵に砕け散る」。
まさに「身体の壊滅」感です。

また東京大学の教授だった玉城康四郎氏も
著書「ダンマの顕現」の中で、自らの「見性」体験を述べていますが、
やはり同じように「身体の壊滅」感があったことを述べています。
奇しくもアーチャン・チャーと同じ「木っ端微塵」と言っています。
要約して引用しますと、
「十地経を取り出して見ていたところ、
何の前触れもなく突然、大爆発した。
木っ端微塵、雲散霧消してしまったのである。」
とあります。
アーチャン・チャーと同じように「木っ端微塵」と表現しています。
「身体の壊滅」感です。
「爆発」。
玉城康四郎氏の「身体の爆発」「木っ端微塵」の感覚は、
「有身見」が断滅する体験であろうと思います。

◆「見性」「有身見が切れる」ときに身体の崩壊感をともなう
で、この悟った瞬間に感じる「身体の壊滅」感は、
「見性(けんしょう)」したときの感覚として、
表現されることがあります。
「見性」を最初にするときは、理屈の上からいっても、
「有身見」が切れることになりますね。
「有身見」とは「この肉体が自分であると思い込んでいる自己同一性」の見解ですね。
これが切れてしまうのでしょう。
このときに「爆発」「木っ端微塵」、あるいは「自他との区別がなくなる」
「自分が消え去って、大いなる存在に取って代わる」といった、
時空を超越した衝撃的な「身体の壊滅」感をともなうのでしょう。
中でも最初の「有身見」が切れるとき、
いわゆる最初の「見性(道果)」では、
身体が爆発してしまう「壊滅感の体験」を
するのではないかと思います。
「見性(道果)」の際に「有身見」が切れるときは、
今まで「この肉体、身体」が「自分」と思い信じ込んできたものの、
その瞬間に「この肉体、身体は自分でない」ということを
空や爆発感、衝撃、一瞬の拡大感などとともに
豁然として如実に体感します。
これは時空を超えた超越的感覚をともない、
想像や妄想、あるいはアストラル界的な瞑想体験とは
まったく異なる感覚をもたらします。
一刹那の瞬間に体験しますが、
それはもう「悟り」としか言いようのない
強烈かつ本能的な印象とともに、
その人に恒久的な魂の刷新性と、
まったく新しい何かに開けた感覚を与える、
そんな体験が「見性」とか「悟り体験」といった
覚醒体験なのではないかと思います。
おそらくこれが「有身見」が切れる瞬間であり、
「見性(道果)」の体験ではないかと推察いたします。
マハーシ長老の「ミャンマーの瞑想」では、
「対象と念じる心は切断された」といった
一つの公式化したパターン表現となっている感も受けます。
時空を超越した体感を表現したものかもしれませんね。
◆ウ・ウィジャナンダー大僧正と世界平和パゴダ
そういわけでして「ミャンマーの瞑想」は大変、
示唆にも富んでいる書だったりします。
ヴィパサナ瞑想中に起きる身体の異変、
また「道果」に至ったときの体験、
大変興味深くまた参考になります。
ちなみに翻訳されたウ・ウィジャナンダー大僧正は、
北九州市にある「世界平和パゴダ」に在住されていましたね。
◎世界平和パゴダ
http://www.worldpeace-pagoda.net/index.html
◎ふるさと探訪|世界平和パゴダ
http://www.nhk.or.jp/kitakyushu/furusato_tanbo/kitakyushu_09.html
◎ミャンマー仏教を語る:世界平和パゴダの可能性
http://amazon.co.jp/dp/4774514683
ウ・ウィジャナンダー大僧正が翻訳してくださったお陰で、
マハーシ長老の名著「ミャンマーの瞑想」を
拝読することもできますね。
ありがたい限りです。
![ミャンマーの瞑想[マハーシ長老]~道果の状態と奇景八触にも言及した希有の名著 ミャンマーの瞑想[マハーシ長老]~道果の状態と奇景八触にも言及した希有の名著](http://img01.hamazo.tv/usr/h/e/a/healingmusic/myanmameisou.jpg)
レナード・ジェイコブソン
エックハルト・トール「さとりをひらくと人生はシンプルで楽になる」
elfin(エルフィン)【2019年12月増刊号】にプラユキさんが紹介
名色分離智とは見清浄であり最初の洞察智~ウ・ジョーティカ氏「自由への旅」
プラユキさん新刊著書のお知らせ~「悟らなくたって、いいじゃないか 普通の人のための仏教・瞑想入門」
ウ・ジョーティカ「自由への旅」~清浄道論に基づく最高の仏教書
エックハルト・トール「さとりをひらくと人生はシンプルで楽になる」
elfin(エルフィン)【2019年12月増刊号】にプラユキさんが紹介
名色分離智とは見清浄であり最初の洞察智~ウ・ジョーティカ氏「自由への旅」
プラユキさん新刊著書のお知らせ~「悟らなくたって、いいじゃないか 普通の人のための仏教・瞑想入門」
ウ・ジョーティカ「自由への旅」~清浄道論に基づく最高の仏教書