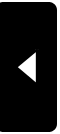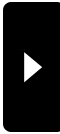さて、この前(2014年)の10/4に、仏教史のセミナーを開催いたしました。
http://healingmusic.hamazo.tv/e5556078.html
◆インド仏教史の変遷
仏教を理解する上で、仏教史を知っておくことは必須であると思っています。
仏教史のポイントを押さえた上で、ある程度、理解できますと、
仏教そのものがよく分かるようになると思っています。
最近では、大乗仏教が非正統であるとか、とかく叩かれ気味な傾向も
見受けられますが、実はこれは少々短絡的なものと考えています。
そもそも大乗仏教は、初期、中期、後期の三期にわけられます。
初期は、「空」の思想。
中期は、「如来蔵」と「唯識」の思想。
後期は、初期の空と中期の唯識を合体させて密教が起こります。
しかし密教の最後期は、「秘密集会タントラ」が登場し左道化していきます。
ちなみにインド仏教においては、仏教が滅ぶ最期の最期まで、
部派仏教(原始仏教)が主流派だったものです。
原始仏教は消滅して、大乗仏教が優勢を占めていたわけではないんですね。
原始仏教(部派仏教)は、最期まで主流派の仏教でした。
【参考記事】
インド仏教史:知られざる本当の歴史
◆初期大乗における「空」
後期密教は別にして、初期大乗の「空」は、
そもそも原始仏教にもある思想です。
具体的には「スッタニパータの1119」にある通りで、
「自我に執する見解を除いて世間を空と観察せよ」
とあります。

初期大乗の「空」は、当時、歪みはじめていた
「部派仏教」の説一切有部を論破し是正するために、
「龍樹」が提唱したことですね。
◆部派仏教を批判するために「小乗仏教」と揶揄した
またこの「部派仏教」を「小乗仏教」と揶揄して、
本来のブッダの仏教に立ち戻る姿を「大乗仏教」と呼称したことも
おおよそわかっています。
当時、部派仏教は何かと問題があったようでして、
龍樹が強調した「空」は、初期大乗の中心的な思想になっています。
龍樹は、「空」(それと空間的縁起観)を打ち出すことによって、
歪んだ部派仏教を軌道修正し、お釈迦さまの理念に戻そうとしています。
で、このときの「空」が初期大乗の象徴にもなっています。
ですから初期大乗仏教は、法華経は別にして、
お釈迦さまへ原点回帰を図った運動だったとみなすことができます。
もっとも龍樹が「空」(それと空間的縁起)を言い出す前から、
初期大乗経典では「空」を中心思想として述べています。
ここを無視して「原始仏教だけが正しい」とするスタンスは
さすがに言い過ぎにもなってまいります。
◆中期大乗における「如来蔵」~極光浄と自性清浄心
また中期大乗の「如来蔵」は、
原始仏教の部派仏教時代に登場もしています。
たとえば大衆部の「自性清浄心」がそうです。
もっとも「パーリ増支部 第一集 弾指品」には、
「心は極光浄にして、随煩悩に雑染されたり」
「心は極光浄にして、それは随煩悩に解脱せり」
ともあって、心が清浄であり、
大衆部の「自性清浄心」と同じことが述べられています。
大乗仏教の中心的な思想は原始仏教にあるわけでして、
いたずらに大乗仏教を否定するのは
原理主義になってしまう恐れもあると思います。
◆日本の仏教は信仰型宗教であり国家安泰を願うために輸入した異形の仏教
また日本の仏教は、大乗仏教になりますが、
インドの大乗仏教とは異なります。
日本は大乗経典に基づき、如来や菩薩を信仰する
信仰型宗教に変容しています。
これはインドの大乗仏教とも異なりますし、
仏教そのものとはまったく異なるスタイルになります。
また日本の仏教は、中国から輸入した仏教になります。
中国仏教を、そのまま日本に移行したところもあります。
ですので日本の仏教は「支那仏教」になります。
元々、日本における仏教は、
日本の神々よりも力のある神の一種の感覚で受容した
歴史があります。
また祖霊崇拝の中でも受容されてきた歴史があります。
それと仏法に従うことで国家が安泰し繁栄するといった
いわゆる鎮護国家としての仏教であったことは、
歴史でも学んだこともあると思います。
「金光明経」を初期には導入したのは、
まさに鎮護国家が目的ですね。
「金光明経」は、中国でも採用された大乗経典で、
日本もこれに右ならえとなった感もあります。
◆日本の仏教は変容した中国仏教
その中国ですが、紀元前100年頃から仏教を導入し始めましす。
が、初期の頃は誤訳が多く、しかも仙道・道(タオ)の一つとして
禅や瞑想のみが輸入された歴史もあります。
中国において仏教的な思想が取り入れられるのは、
ずっと後になってからだといわれています。
また中国では、華厳宗、真言宗、曹洞宗といった
仏教宗派が誕生しています。
日本は、こうした「中国系仏教」を輸入し、
なおかつ日本の始祖達が経典等を選択(せんじゃく)し、
独自の仏教を作り上げていきます。
ですから、日本の仏教では、始祖・開祖達の語録が重視され、
曹洞宗における正法眼蔵、浄土宗の「選択本願念仏集」、
真宗の「教行信証」などはその典型です。
こうした開祖の「語録」を重視する傾向が、
日本の仏教の特徴でもあって、ここも日本仏教における
一つの大きな課題にもなっていると考えられます。
◆テーラワーダ仏教は「分別説部」の三蔵を依経とした部派仏教の末裔
その点、テーラワーダ仏教圏では、まず最初に
紀元前250年頃にスリランカにパーリ仏典が伝承されます。
アショーカ王の長男のマヒンダが伝えたことは、
わりと知られていることと思います。
パーリ仏典は、パーリ語で書かれているので、
そのように言われていますが、詳しいことをいいますと、
部派仏教の「分別説部(スリランカ上座部)」が保持していた三蔵になります。
実のところ部派仏教内でも、経典の構成や中身には
違いがあります。
また全ての部派が、三蔵を有していましたので、
パーリ仏典だけが唯一の原始仏典とするのは、
さすがに行き過ぎになります。
ただしパーリ仏典は、現存する唯一の完全な原始仏典になります。
そういう意味で貴重な仏典といえるかと思います。
◆漢訳阿含経とパーリ仏典との違い
ちなみに漢訳阿含経(中国に輸入された根本仏教経典)と、
パーリ経典とでは、中身にかなりの違いもあります。
経典数すら異なります。
率直にいいますと、漢訳阿含経は資料的な価値はあっても、
法蔵部、説一切有部、大衆部などのバラバラの寄せ集めです。
しかも中国人が翻訳していますので、
果たしてどこまで信用していいのか少々疑問があります。
その点、パーリ仏典は整然と全てがそろっていますし、
また論蔵の点においても、当時、部派仏教では最大派閥でもあり、
なおかつ問題のあった「説一切有部」を否定しています。
「説一切有部」は、存在原理まで究明しようとしています。
中でも「三世実有・法体恒有」でも有名な
特殊な縁起観を打ち出しています。
お釈迦さまが言及されなかった世界へと足を踏み入れ、
この高踏的なスタンスが、当時「小乗仏教」と
揶揄されることにもなっています。
いわば説一切有部が原始仏教を破壊した
張本人とも読み取ることもできます。
ですから部派仏教(説一切有部)は、
その後、龍樹によって論破されることにもなります。
そして大乗仏教の趨勢が強まります。
パーリ仏典は、原始仏典の中でも、
信用がおける経典ではないかと思います。
漢訳阿含経は、切一切有部所有のものが含まれていますし、
また論蔵に到っては、説一切有部のものになります。
と、こういったことなどを、この前はお話しいたしました。
発菩提心・回心は大切
瞑想では意欲・熱量が大切
気功と瞑想は同じ~2022.10.23静岡県掛川市気功講習会
瞑想がうまくいかない場合の3つの解決策・対策
「あるがまま」を妨げるサンカーラの解消方法
アーチャン・ニャーナラトー師瞑想会 法話~愛知県豊田市 弘誓院【2019年9月28日(土)】
瞑想では意欲・熱量が大切
気功と瞑想は同じ~2022.10.23静岡県掛川市気功講習会
瞑想がうまくいかない場合の3つの解決策・対策
「あるがまま」を妨げるサンカーラの解消方法
アーチャン・ニャーナラトー師瞑想会 法話~愛知県豊田市 弘誓院【2019年9月28日(土)】